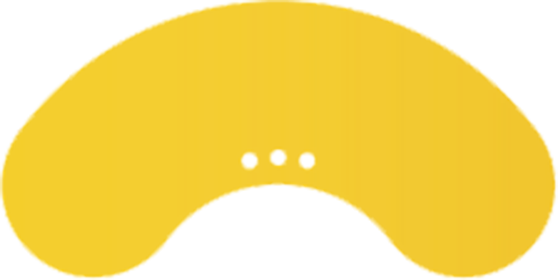~SHIMANTO Brewing 岡林 孝典さん・明子さん~
好きなことを仕事に!サーフィンと出会いが導いた四万十でのビールづくり

清流・四万十川と豊かな自然に恵まれた四万十市。その一角にある歴史ある酒屋が、新たにクラフトビールの拠点へと生まれ変わりました。手がけるのは、大阪から移住した岡林孝典さん・明子さんご夫妻。サーフィンがつないだ縁が、四万十の街に新しい風を吹き込んでいます。
お二人のこれまでの歩みと、起業に込めた想いを伺いました。
移住、そして「ここでしかできない仕事」を求めて

お二人は四万十市に移住されたそうですね。きっかけは何だったのでしょうか。
(明子さん)
私は兵庫県出身で、大阪の新聞社に勤めていました。夫の趣味がサーフィンで、結婚後に私も始め、月に1度は一緒に四万十の海へ来ていたんです。
そんな時、仲間から『家を建てるから、今の家を借りないか』と声をかけられ、見に行ったらとても素敵で。別荘感覚で借りたのですが、だんだん“ここに住みたい”と思うようになり、2016年に思い切って移住しました。
(孝典さん)
私は高知市生まれの関西育ち。設備関係や大工の仕事をしてきましたが、サーフィンのために20年近く高知に通っていました。だから移住は自然な流れだったのかもしれません。
移住後すぐに起業を考えていたのでしょうか。
(明子さん)
最初、四万十市観光協会でふるさと納税の商品開発に携わった後、大手ビール会社の営業に転職しました。
直行直帰の勤務形態だったので、サーフィンを楽しみながら働ける環境で、ビールの知識も深まっていきました。もともとクラフトビール好きだった私は、次第に“自分でも造ってみたい”と思うようになったのです。
ただ、当時は収入も安定していたので、起業はまだ現実的ではありませんでした。
(孝典さん)
私は運送会社で働いていましたが、“いつかは自分で何かを”という思いは持ち続けていました。
大家さんの一言から動き出した起業

実際に起業されたきっかけは何だったのでしょうか。
(明子さん)
サーフィン仲間でもある、今の拠点の大家さんから『自分たちで何かやらないの?』と、物件を紹介してもらったことがきっかけでした。
ここは、かつて造り酒屋として歴史のある建物で、酒税法の改正を機に酒造りをやめ、その後は町の酒屋として続いてきた場所でした。近年は卸売が中心となり、長らくシャッターが閉まったままでしたが、ここを活用して“クラフトビールを造れたら”と思ったんです。
ふるさと納税の商品開発に携わっていた頃から、「地元の人が誇るもの」と「都会の人が求めるもの」の間にあるギャップをどう埋めるかを意識していた私にとって、その経験を活かせる場がまさにここにあると感じました。
そこで大家さんに『この場所を貸してください』とお願いし、挑戦を決意しました。
実際にどのように起業を進めていったのでしょうか。
(明子さん)
まずは設備を整えることを考えましたが、タンクや醸造設備は高額で、自己資金では足りません。
また、ビール造りの経験がないため、どこから手をつけたらいいのか分からず、研修先もなかなか見つかりませんでした。
そんな時、『高知 起業』で検索して出会ったのが『こうちスタートアップパーク(以下、KSP)』でした。起業相談では、事業計画の立て方や資金調達の流れを教えてもらい「地域課題解決起業支援事業費補助金」を紹介してもらいました。『いい計画なので頑張ってください』と励まされ、背中を押してもらえたのが心強かったですね。また、研修先として福岡県糸島市のブルワリーに受け入れていただき、週末などを活用して通いながら学びました。
起業するにあたり、大変だったことなどはありましたか。
(明子さん)
とにかく一番の課題は資金でした。そのため起業コンシェルジュから紹介してもらった『高知県地域課題解決起業支援事業費補助金』と銀行融資を組み合わせる形で進めました。
まず、KSPの「事業計画策定セミナー」にも参加し、セミナーで学んだ内容を基に事業計画を練り上げました。もともとは、補助金の申請に向けてセミナーに参加をしましたが、そこで学び、練り上げた事業計画の内容で銀行からの融資にもつながりました。補助金の申請準備で作成した事業計画書が金融機関にも評価され、スムーズに手続きが進んだのは大きな成果でした。
起業自体は2~3年前から考えていましたが、実際に動き出してからは約1年で開業までたどり着くことができましたね。
(孝典さん)
開業までは時間との闘いでした。店舗のカウンターなども手作りし、準備に追われました。
酒屋の建物が生んだ「0次会文化」

本当に素敵なお店ですよね。空間づくりの随所に、ご夫婦ならではの工夫とこだわりが伝わってきます。
商品づくりにおいては、どのような点を大切にされているのでしょうか。
(明子さん)
醸造免許の取得はハードルが高く、申請から許可が下りるまでに想像以上の時間がかかりましたが、ようやく取得できました。これまではうちのレシピを基に糸島市のブルワリーで造ったビールを販売してきましたが、現在は自社設備で初回の仕込みを終えていて、自家醸造ビールをお届けできる日が近づいています。念願の1stバッチの完成が待ち遠しいです。
これまでの委託醸造では、“飲みやすさ”を意識してきました。クラフトビールは多様性が魅力ですが、まだまだクラフトビールの文化が根付いていないことから、まずは手に取りやすい味わいから広げていきたいですね。そして、地元の食材を使うということもこだわっています。これまでに手掛けた、無農薬レモンを使ったセゾンビールは地元の農園のPRにもつながりました。
四万十ひのきや四万十川の伏流水など、挑戦したい素材はまだまだあります。
(孝典さん)
店舗は酒屋の建物を活かし、ワインセラーの窓を残して歴史を引き継ぎました。蔵造りのため温度変化も少なく、落ち着ける空間になっています。
(明子さん)
“0次会文化”も提案しました。四万十市には飲み会前に気軽に立ち寄れる場所がほとんどなかったので、そんなお店があればいいなと思っていたんです。
それが地元の方にも受け入れられ、今では夕方に1〜2杯飲んでから出かけるスタイルが少しずつ定着しています。お客様から『こういう場所を待っていた』と言っていただけるのは、本当にうれしいですね。
クラフトビール市場は今、急拡大していますが、他社との差別化はどのように考えていますか。
(明子さん)
事業規模の拡大を目指すのではなく、地元での需要を広げていきたいと考えています。クラフトビールの市場は急速に拡大していますが、“四万十”という名前だけでは有名ブルワリーには敵いません。
だからこそ、無理に外で競うのではなく、この地でローカルビールとして根付かせたいのです。
『四万十に行ったらおいしいビールがある』と思ってもらえる存在になりたい。そして関西などで知ってくださった方が、『四万十ってどんなところだろう?行ってみたいな』と足を運んでくれるようになれば理想ですね。
起業して広がる可能性

実際に起業してみて、よかったと感じるのはどんな瞬間ですか。
(明子さん)
自分ですべて決められる自由度が高いところですね。お客さんからのアイデアが次々に生まれるのも楽しいです。例えば、地元の土佐くろしお鉄道とコラボをした企画など、まだ実現していないものもたくさんありますが、起業したことで、地元の方や地域とのつながりが広がりました。
今後は、どのようなことに取り組もうと考えられているのでしょうか。
(明子さん)
自家醸造が始まり、自分たちの手で造ったビールをお届けできる体制が整いました。今後は、通販、ふるさと納税、道の駅などへの展開も進めたいと考えています。
店内で造り方の実演やフードペアリングの提案などもして、クラフトビールを楽しむ文化を広げたいですね。将来的にはクラフトビールフェスのようなイベントができれば、と考えています。
(孝典さん)
ビールを造るときに出る麦芽かすは、養鶏場で鶏の餌として活用し、その鶏が産んだ卵を使った料理をここで提供したいと考えています。さらに、鶏のフンはレモンの肥料になり、そのレモンを再びビール造りに…。そんな循環型の仕組みに挑戦したいですね。
加麦芽かすで染めたオリジナルTシャツの制作も予定しています。
これから高知で起業したいと考えている方へメッセージをお願いします。
(明子さん)
大切なのは“やりたいことを口にすること”。計画が固まっていなくても、人に話すことで道が拓けます。私もクラフトビールを造りたいと言った瞬間から、出会いや協力が一気に広がりました。
高知は不便さもあるけれど、それを逆手に新しい挑戦ができる場所。とにかく大事なのは、“熱意”と“行動力”です。
(孝典さん)
お金のことはしっかり準備した方がいいですが、やってみれば何とかなる部分もあります。まずは一歩を踏み出すことが大切です。

SHIMANTO brewing
・住所:高知県四万十市中村本町1丁目21番地
・HP:https://www.instagram.com/shimantobrewing/?hl=ja
文責/是永 裕子